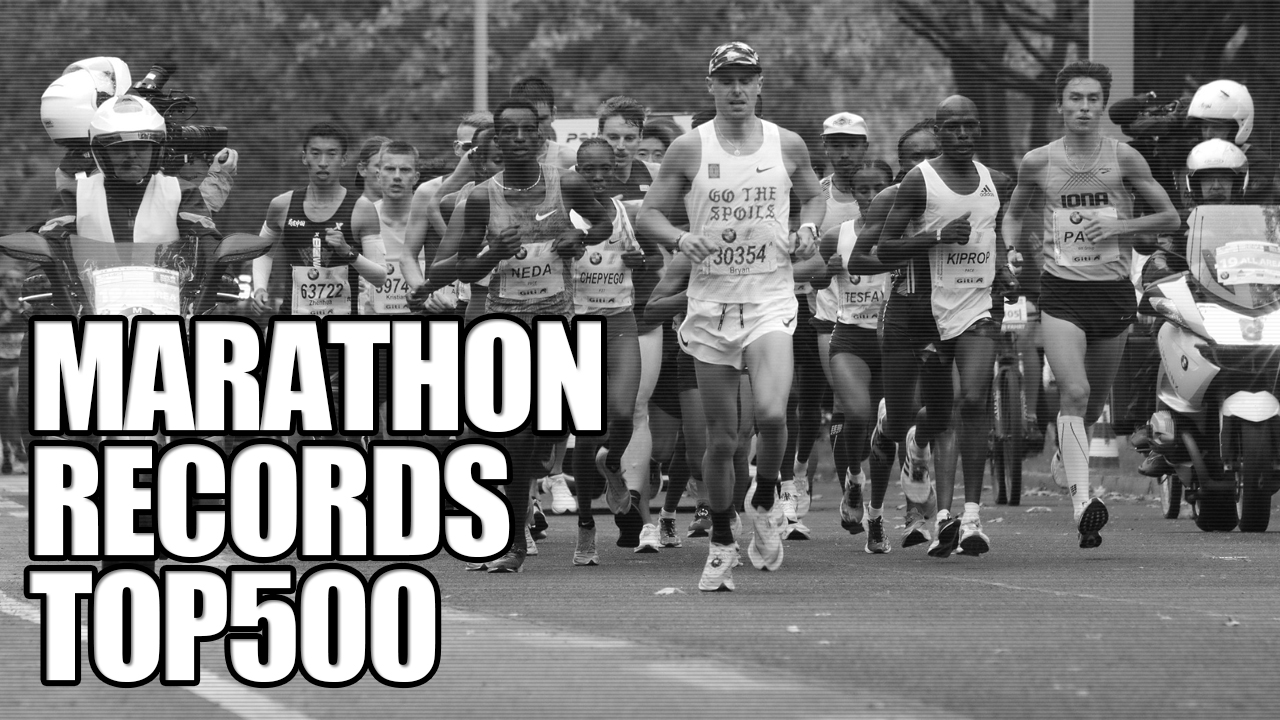マラソンという競技が、どのようにして今日の形になったのかご存知ですか?その背景には、古代ギリシャの故事から近代オリンピックでの数々のドラマ、そして科学の進化が詰まっています。

マラソンの始まり
マラソンの起源は、紀元前490年の「マラトンの戦い」に遡ります。ギリシャ軍がペルシャ軍に勝利した際、伝令兵のフィリッピデスがマラトンからアテネまで約40kmを走り、「喜べ、勝利だ!」と勝利を告げた後に力尽きて絶命したという故事が、マラソンの名の由来とされています。
近代オリンピックと距離の標準化
マラソンの登場と初期の混乱
マラソンが初めて近代オリンピックで実施されたのは、1896年の第1回アテネオリンピックです。この時の距離は約40kmでしたが、当初は大会ごとに距離が異なり、「約40km」という曖昧なルールで運用されていました。
42.195km誕生のドラマ
現在の42.195kmという距離が決定されるきっかけとなったのは、1908年の第4回ロンドンオリンピックです。イギリスのアレクサンドラ王女が「スタートは宮殿の庭から見えるように、ゴールは競技場のボックス席の前に」と要望したため、当初予定の約42kmに385ヤード(約352m)が追加され、結果的に42.195kmとなりました。
このロンドン大会での出来事や、イタリアのドランド・ピエトリ選手の悲劇的なエピソードが、現在の距離が正式に採用される大きな要因となりました。
ドランド・ピエトリ選手の悲劇
1908年ロンドンオリンピックのマラソン競技で、イタリア代表のドランド・ピエトリ選手は、競技場にトップで入ってきました。しかし、極度の疲労と脱水症状のため意識が朦朧とし、コースを間違え何度も転倒します。
観客の大歓声の中、彼は役員や医師に助けられながらもゴールを目指し、最終的には係員の助けを借りて1着でゴールラインを越えました。しかし、外部からの援助があったため、アメリカチームからの抗議により失格となってしまいます。金メダルは2着だったジョニー・ヘイズ選手(アメリカ)に与えられました。
この出来事は「ドランドの悲劇」として語り継がれ、多くの人々に感動を与えました。アレクサンドラ王妃は、彼の勇敢な走りを称え、特別に金色のカップを贈呈しました。このドラマチックな出来事が、マラソン競技の距離が42.195kmに正式に定められるきっかけの一つになったと言われています。
オリンピックマラソンの距離の変遷(第1回〜第7回)
1921年に国際陸上競技連盟(現ワールドアスレティックス)が42.195kmを正式なマラソン距離として採用し、1924年の第8回パリ大会からこの距離で実施され、現在に至ります。
それまでのオリンピックマラソンの距離は厳密には固定されておらず、大会ごとに異なりました。
- 第1回アテネオリンピック(1896年): 40km
- 第2回パリオリンピック(1900年): 40.26km
- 第3回セントルイスオリンピック(1904年): 40km
- 第4回ロンドンオリンピック(1908年): 42.195km(現在の距離が偶然にも設定された大会)
- 第5回ストックホルムオリンピック(1912年): 40.2km
- 第6回ベルリンオリンピック(1916年): 第一次世界大戦のため中止
- 第7回アントワープオリンピック(1920年): 42.75km(オリンピックマラソン史上最長)
オリンピック以外のマラソンレース
初期のオリンピックマラソンの成功に触発され、世界各地でマラソン大会が開催されるようになりました。特に有名なのが、ボストンマラソンです。
1897年に第1回大会が開催され、これは毎年開催されるマラソン大会としては世界で最も古い歴史を誇ります。その他にも、1902年の「ツール・ド・パリ・マラソン」や1907年の「ヨンカーズ・マラソン」など、様々な大会が生まれましたが、これらのレースも1908年のロンドンオリンピックまでは距離がまちまちでした。
近代オリンピック以前の「長距離走」
近代オリンピック以前にも長距離走は存在しましたが、現代の競技とは大きく異なりました。
古代オリンピックのドリコス走
古代オリンピックには、紀元前720年から導入されたドリコス走という長距離走がありました。スタディオン(スタジアム)の直線路を何度も往復する形式で、距離は約3.8km程度だったとされます。現代のようにタイムを計測するのではなく、駆け引きや最後のスパートで勝負が決まる要素が大きかったようです。
しかし、「マラトンからアテネへ伝令が走った」という故事はあっても、それを競技化した「マラソン」は古代オリンピックにはありませんでした。
世界各地の「長距離走」の文化
厳密なルールやタイム計測を伴う現代の競技とは異なる形で、世界各地には「長距離走を競う競技」や「祭り、儀式の一環としての走り」が存在していました。
- 古代メソアメリカ文明(マヤ、アステカなど): 長距離の伝令が重要な役割を担い、時には数百キロメートルを数日で走破しました。その能力は競われ、尊敬の対象でした。
- アメリカ大陸の先住民部族(ホピ族、ズニ族など): 狩猟、伝令、移動、そして宗教的な儀式や祭りに走ることが不可欠でした。部族間の競争や、雨乞いの儀式として長時間走り続ける「走り」が行われていました。
- アフリカ大陸: 部族社会において長距離の移動能力や伝令の役割が重要で、戦士の訓練として長距離走の持久力が養われました。
- 江戸時代の日本: 遠隔地への情報伝達手段として「飛脚」が発達し、長距離を走破しました。また、修験道では山中を走り続ける「行(ぎょう)」があり、精神的な鍛錬として超長距離を走る要素が含まれていました(例:千日回峰行)。
これらの例は、古代から近代に至るまで、人類が様々な目的(実用、信仰、競争、訓練など)のために長距離を走る活動を行い、それを競い合う、あるいは祭事や儀式として位置づけていたことを示しています。
マラソン記録の驚くべき進化
マラソン距離が42.195kmに統一された1921年以降、世界記録は驚異的なペースで短縮されてきました。
男子マラソン世界記録の推移
国際陸上競技連盟が最初に公認した男子マラソンの世界記録は、アルベルト・ミケルセン(アメリカ)が1925年に記録した2時間29分01秒8です。これは人類で初めて2時間30分の壁を破った記録でもあります。
以下に、記録短縮の推移を10年ごとに見てみましょう。
- 1925年〜1935年頃:
- 1925年10月12日:アルベルト・ミケルセン(アメリカ) 2時間29分01秒8
- 1935年3月21日:孫基禎(日本/当時) 2時間26分14秒
- 短縮幅: 約2分47秒8
- 1935年〜1945年頃:
- この期間は記録更新なし。
- 短縮幅: 0秒
- 1945年〜1955年頃:
- 1952年6月14日:ジム・ピーターズ(イギリス) 2時間20分42秒2
- 短縮幅: 約5分31秒8
- 1955年〜1965年頃:
- 1965年6月12日:重松森雄(日本) 2時間12分00秒
- 短縮幅: 約8分42秒2
- 1965年〜1975年頃:
- 1969年5月30日:デレク・クレイトン(オーストラリア) 2時間08分33秒6
- 短縮幅: 約3分26秒4
- 1975年〜1985年頃:
- 1985年4月20日:カルロス・ロペス(ポルトガル) 2時間07分12秒
- 短縮幅: 約1分21秒6
- 1985年〜1995年頃:
- 1988年4月17日:ベライネ・デンシモ(エチオピア) 2時間06分50秒
- 短縮幅: 約22秒
- 1995年〜2005年頃:
- 2003年9月28日:ポール・テルガト(ケニア) 2時間04分55秒
- 短縮幅: 約1分55秒
- 2005年〜2015年頃:
- 2014年9月28日:デニス・キメット(ケニア) 2時間02分57秒
- 短縮幅: 約1分58秒
- 2015年〜2025年(現在):
- 2023年10月8日:ケルビン・キプタム(ケニア) 2時間00分35秒
- 短縮幅: 約2分22秒
初期の大きな短縮から、近年はシューズの進化やトレーニングの科学化により、記録更新のペースが加速しています。
女性マラソンの歴史と飛躍
女性がフルマラソンに参加し、完走した歴史は男性に比べて新しいものです。かつては女性が長距離を走ることは身体的に不可能、あるいは不適切だと考えられていました。
壁を破った女性たち
この歴史を大きく変えたのが、ボビー・ギブとキャサリン・スウィッツァーです。
- ボビー・ギブ(1966年ボストンマラソン): 公式登録なしに飛び入り参加し、完走した最初の女性です。非公認ながら、女性がフルマラソンを完走できることを示しました。
- キャサリン・スウィッツァー(1967年ボストンマラソン): 公式ゼッケンをつけて走った最初の女性。レース中に大会役員に止められそうになる有名な事件がありましたが、完走しました。この出来事は、女性がマラソンに参加する権利を求める運動の象徴となりました。
彼女たちの努力と勇気が、その後の女性マラソンの発展に大きく貢献し、1972年にはボストンマラソンが女性ランナーの参加を正式に認め、1984年のロサンゼルスオリンピックでは女子マラソンが正式種目となりました。
女性マラソン世界記録の推移
女性のフルマラソン公式記録は、1960年代後半から1970年代初頭に始まりました。
基準点: 1970年2月28日 キャロライン・ウォーカー(アメリカ) 3時間02分53秒
- 1970年〜1980年頃:
- この10年間は女性の参加が急速に広まり、記録が飛躍的に短縮。
- 1979年10月21日:グレーテ・ワイツ(ノルウェー) 2時間27分33秒
- 短縮幅: 約35分20秒
- 1980年〜1990年頃:
- 1985年4月21日:イングリッド・クリスチャンセン(ノルウェー) 2時間21分06秒
- 短縮幅: 約4分36秒
- 1990年〜2000年頃:
- 1999年9月26日:テグラ・ロルーペ(ケニア) 2時間20分43秒
- 短縮幅: 約23秒
- 2000年〜2010年頃:
- 2003年4月13日:ポーラ・ラドクリフ(イギリス) 2時間15分25秒
- 短縮幅: 約5分18秒(ポーラ・ラドクリフが大きく短縮)
- 2010年〜2020年頃:
- 2019年10月13日:ブリジット・コスゲイ(ケニア) 2時間14分04秒
- 短縮幅: 約1分21秒
- 2020年〜2025年(現在):
- 2024年10月13日:ルース・チェプンゲティッチ(ケニア) 2時間09分56秒 (※記録は承認待ちの可能性あり)
- 短縮幅: 約4分08秒
女性のマラソンにおける記録の進化は、競技力向上だけでなく、女性のスポーツ参加に対する社会的な認識の変化と、それに伴う環境整備の歴史を反映しています。
マラソン記録進化の要因
この驚異的なタイムの進化は、単に選手の能力向上だけでなく、様々な要因が複合的に絡み合って実現されています。
1. トレーニング方法の進化と科学的アプローチ
かつては経験則に基づいたトレーニングが主流でしたが、現在では生理学、栄養学、心理学など、様々な科学的知見に基づいたトレーニングが導入されています。高地トレーニング、インターバルトレーニング、LSD(ロングスローディスタンス)など、目的に応じた多様な手法が確立され、選手一人ひとりに最適化されたプログラムが組まれています。
2. 栄養と水分補給の重要性の理解
レース中の適切な水分・電解質補給、カーボローディングなどの栄養戦略が確立され、選手のパフォーマンス維持と回復に大きく貢献しています。
3. 用具の進化
- シューズ: クッション性、反発性、軽量性を追求したランニングシューズの進化は、タイム短縮に大きく寄与しています。特に近年では、カーボンプレートを内蔵したシューズが記録更新の大きな要因です。
- ウェア: 通気性や軽量性に優れた高機能素材のウェアも、選手の快適性を高め、パフォーマンスをサポートしています。
4. コースの高速化とペースメーカーの導入
世界記録が生まれるような主要なマラソン大会は、高低差が少なく、風の影響も受けにくい高速コースが選ばれる傾向にあります。また、エリートレースでは、設定されたペースで選手を引っ張る「ペースメーカー」の存在が不可欠です。これにより、選手は安定して高速でレースを進めることができ、記録更新の可能性が高まります。
5. 競技人口の増加と競争の激化
マラソンが世界中で人気を集め、競技人口が増加したことで、才能ある選手がより多く輩出されるようになりました。トップレベルでの競争が激化することで、選手たちは互いに高め合い、より速いタイムを目指すモチベーションとなっています。
6. 距離の標準化
1921年にマラソン距離が42.195kmに統一されたことで、異なる大会や時代の記録を比較することが可能になり、記録更新の意義が明確になりました。
これらの要因が複合的に作用し、男子マラソンの世界記録は、現在では2時間0分台にまで短縮されています。人類初の2時間切りも、そう遠くない未来に実現されるのではないかと期待されています。
マラソンは、たった一人の伝令兵の故事から始まり、人々の挑戦と進化の歴史を刻んできました。科学的なトレーニング、革新的なシューズ、そして世界中のランナーの情熱が融合し、記録は今も伸び続けています。
人類初の「2時間切り」という究極の目標は、もはや夢物語ではありません。この挑戦は、多くのランナーに希望を与え、私たち自身の限界を超えていく可能性を示してくれるでしょう。